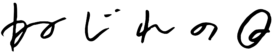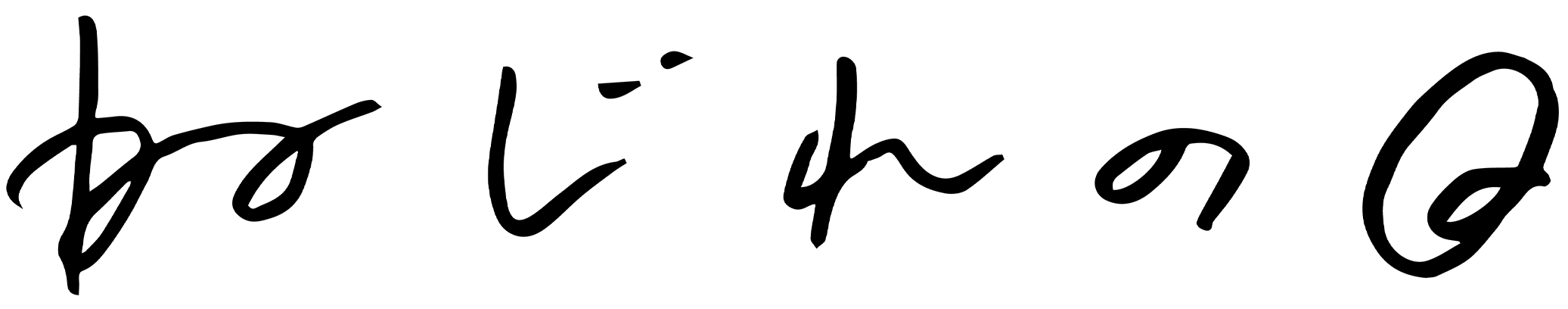二連休があるので、岡山に帰ることにする。
瀬戸大橋を渡るときの気持ちのしずまる感覚がいつも独特だ。
前日の即興ワークショップでは直後の振り返りがいちばん厚めにとれた回だとおもう。雑多な要素が組み合わさる音楽の場なので、音楽を感じとる受信機として聴覚以外の「視覚」や「触覚」をまとうことは常だったが、振り返りやアイデア/ブレストの場では、またさらに別の「嗅覚」や「味覚」にも話が及んだ。
その余韻で表町商店街のアーケードをあるけば昔ながらのお店に感覚が向かうのが何らふしぎでない。刃物屋さんでざらざら砥石を購入し、仏具屋さんで塗香を購入。たくさんのスパイシーな匂いを探検し、菌類のような配置の数珠のお話を聴き、奥で木魚もぽくぽくたたかせていただいた。
さて、表町の一本道には、端と端に文鎮を置くようにして、文化施設が親子か兄弟のように配置されていることをご存知だろうか。片方はわたくしが子どもの頃からよく馴染んだ岡山シンフォニーホールで、もう片方は一昨年オープンしたばかりの岡山芸術創造劇場ハレノワである。こちらはまだ一度も入ったことがなかったので、訪ねてみたいと思っていたところだった。しんとしたひとの気配のないエントランス、たくさんのチラシラック、たまに姿を見せる表現者の風をしたひとたちの姿に、嫌でも雑多で賑やかな自分のいつもの現場が想起された。前々日の企画で来訪された京都の劇場の方との交流の記憶もまだひりひりとあざやかった。
かばんのなかに一冊の本が入っている。協働する音楽家の話を両親に話したら、サイトにアップされたアーティスト写真のクレジットに心当たりがあるという。ジャーナリスト・烏賀陽弘道さん、このひとの本がうちにあると母は棚を指した。この休日は、ふしぎな熱量ですいすい読めてしまう記録とともに過ごす時間ともなった。なつかしきオンサヤや禁酒会館でコーヒーを飲み、広大なアメリカ・原子力開発のための大地とひたむきな研究者たちに想いを馳せる。シネマクレールで映画を観る。いささかくたくたになり、すっかり暮れた電車で地元に帰る。