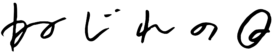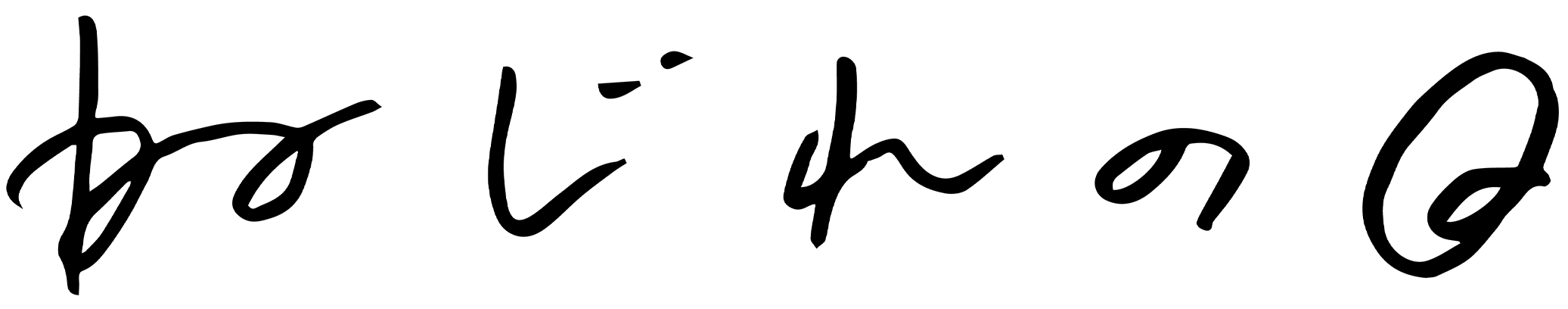20251106
ある夫婦の取材を目論んだところ事態が急変し、かたほうの葬儀への参列となったのが2020年の秋のことである。その日は奇しくも弟の誕生日であった。葬儀から火葬への合間に町を散策し、ねだられた煙草を買ってやったことを覚えている。
当時の祖母は、ゆっくりとだが歩き回ることができていた。葬儀が終われば伴侶にまつわる気持ちの丈をわたしたちに聞かせることもかなった。別れのことを流れる水を掻き寄せるような寂しさがあると喋った彼女。しっかり者の祖母をたくましいなと思った。でも、お土産に買っていったお茶を別のお客さんにすぐ渡す。わたしの書いた手紙は新聞広告の束に埋もれていく。あのころは当たり前に入れていた祖母邸の居間で、半ば呆れた気持ちになったのもなつかしい。
春が来て、秋が来て
春が来て、秋が来て、
春が来て、秋が来て
春が来て、秋が来て、
春が来て、秋が来た。
あの日より、
季節がふたつめぐるたびにいちど
彼女を訪ねる習慣がはじまった。
一瞬だけ会えた日があり、泊まってこんこん話せた夜があった。行き先は深い山奥の家屋から病院になり、病院から施設になった。都合に合わせられた滞在時間は30分間になり、15分間になった。わたしの住む都市は二度変わった。
会いにいくたびに記憶が巻き戻るようあたらしく、古い話をする祖母。思い出が煮込まれ砕け滲むたび、わたしの名前や、病室に訪れる目の前の若者が一体何者かも少しずつゆるく溶けて分からなくなっていくのだった。
10回目を数える今日、彼女は個室にいる。
案内される廊下を歩くときから微かに聞こえていた悲鳴のような声の主であった。病室の彼女の話す言葉は喃語めきており、内容はほとんどわからなかった。ただそれが苦悶の言葉であることはよく伝わった。その様子は私を責めているようでもあった。
なんだか祈りみたいだな
どういうこと?
いま洞窟の中を歩いているんだね
そうよ
とても興味深いです
ほんと?
彼女の音の意味はこちらには分からないけれど、わたしの言葉はすこしだけ届いているみたいだった。白く痩せ皮がすこし余っている手をそっと握ると、とかげを触ったときの記憶がした。
わたしたちの15分間はあまりにも短く
お互いのことはもうほとんどわからない
けれどほんのすこしだけ振動している
ゼリーのような旅に包まれたこの習慣は
わたくしを問い直す時間にほかならない