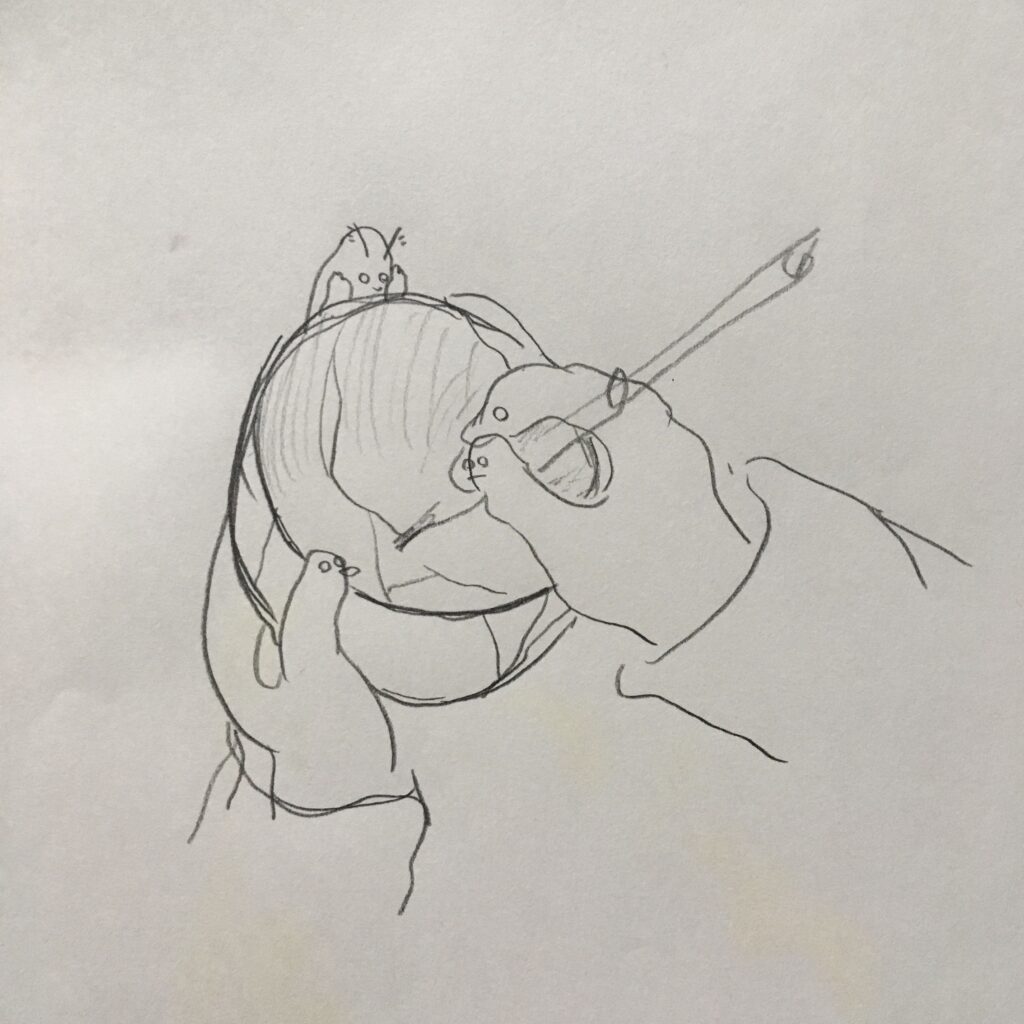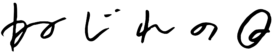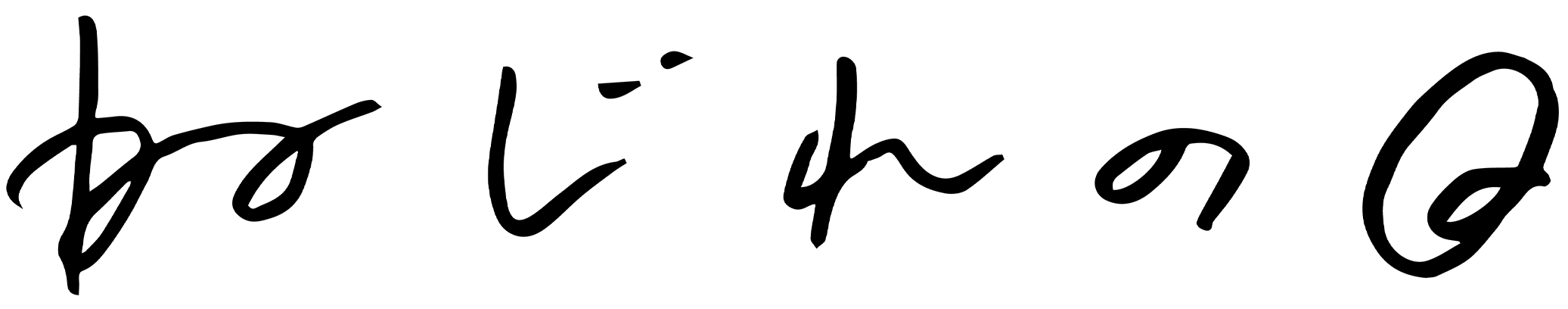漆芸職人のお稽古に昨年の春から通っている。主に「金継ぎ」の教室なのだが、わたしは自分の壊した器の修繕はせず、先生に教わりながら気ままに漆の作品をつくっていた。
お稽古に通い始めた当初、器の金継ぎから入らなかったのには、実はわけがある。というのも、わたしが繕うべき器たちは、すでに1年くらい早く金継ぎ教室に通い始めた同居人のお題となっていたからだった。何を隠そうわたしは破壊のプロである。非情なまでに触ったものを順々に壊す。当時はまだ教室に通っていなかったし、「かやちゃんこれ欠けてる、金継ぎしていい?」と声がかかれば、「やや、お願いします」とお返事しないわけがないのであった。
さて、そんなわたしも最近は真面目に(?)金継ぎに勤しんでいる。いそがしくて夏以降教室に通えない同居人の元に集った「宿題」をやんわり引き継ぐ形で、器を繕い始めたのだ。金継ぎの工程の途中まで進んだ器たちは、馴染みの顔から見知らぬひとまでさまざま。今日は大山の作家、三苫修さんの土星色した器を継いだ。お見事、といいたくなるくらい屈託なく割れた継ぎ目に、慎重に朱を引いていく。
「結構派手にやってますね、難しいですよこれ。」
「まずは内側だけやりない(やってごらん)。ゆっくりやれば大丈夫。」
早いもので、次の春で二年を迎えるマドロミ荘での暮らし。まずはじめに彼女に自分の器を直してもらい、今度は彼女の器を直している。なんだか不思議でおもしろい巡り合わせだなあと思う。