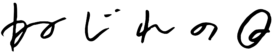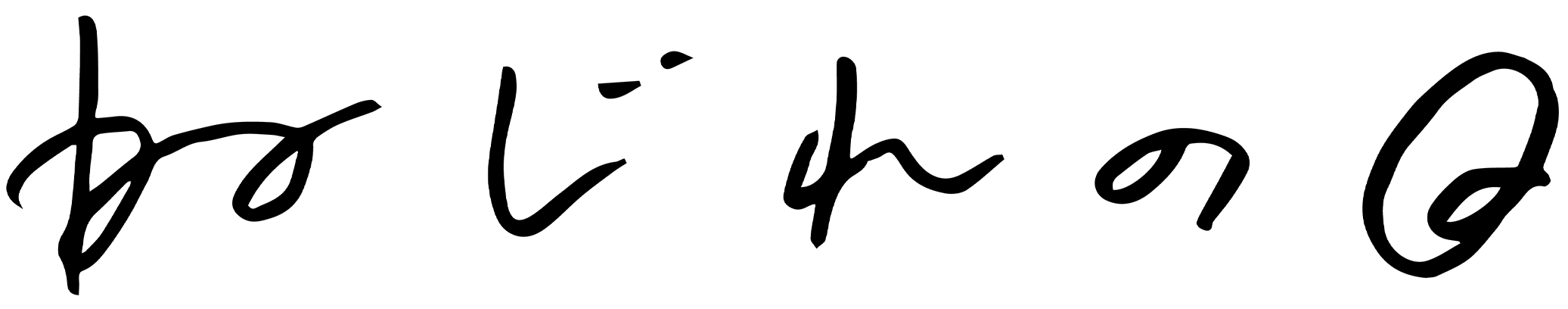疲労を綿にたとえて
朝が起きれない日が続くとそれだなとわかる。意識はまるで掠れペンのさま、線を引いても乾いた点々になってまとまりがない。おや、見渡せばあたりに真綿が充満しているではないか。手に脚に連動する綿。あたたかく、ふわふわとしていて、踏んでも叩いても感触が伝わらない。目に耳に詰まる繊維。これでは音も視界も通さぬ。思わず「ついて回るんじゃない!」と声を上げるも、発声は自慢の防音効果に虚しくすいこまれていった。
ふと、白と白の隙間にうつる
TACETの標識
これではじめて腑に落ちる…
***
仕事の終わったあと、ふたつとなり町に観劇へと向かう。小さな友人の出演もあり、楽しみにしていた今日。舞台上の彼女の、いつもとは違う大人びた姿を愛しく嬉しく思う。ここの作品を観に行くのは二年ぶりで、前回も忘れられない舞台だった。今回の最後の劇中歌は「この世には正義も悪もなく、とどのつまり勝ち負けできまる、だれにも決められない自分を生きろ」とのメッセージ。コロナ禍で常識がぶち壊れていき、舞台の存在が当たり前でなく誰かの灯となること。今現在と真摯に向き合い書かれた作品だと感じる。街の出演者の顔をたくさん思い浮かべたであろうことも。伝わる。胸をうつ。
帰り道、思わず電話した先
ほんのすこし西側の街
おかわり自由の衝動と身勝手の青に
ちょっと呆れた笑い声の混じる